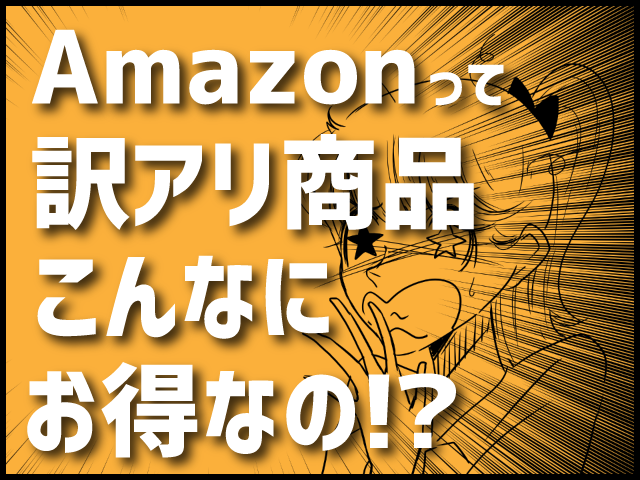オタク界隈でも使われるようになった百合(ゆり)という言葉。
女性同士の同性愛を指し示した言葉(レズ)ですが、百合といわれるようになった由来や意味はなんなのかをまとめました。
下記クリックで好きなところに移動
百合とは?女性同士の同性愛の意味について
百合(ゆり)とは女性同士の同性愛で2人組のことを指します。
俗に言うレズビアンの意味なのですが、一人での場合には「レズ」とは言っても「百合」とは使いません。
百合は「同性愛の女性同士2人でいること」を第三者目線から見た場合のことを言います。
ジャンルとしての意味合いが強く、百合専門誌をはじめ、アンソロジーコミック、同人誌などでも百合という言葉(女性同士のカップリング)を用います。
百合の意味・由来・語源は?なぜ百合なのか?
『胡麻と百合』説
1864年出版の『胡麻と百合』(ジョン・ラスキン著、原文)の書籍のなかで、男性同性愛を「胡麻」、女性同性愛を「百合」に象徴されていました。
百合の語源はここから始まったといわれています。
ちなみに日本では原文『胡麻と百合』よりもフランス語訳された『失われた時を求めて」(マルセル・プルースト訳)のほうが有名になってしまった経緯があります。
プルートス自身もゲイで、作品の中に男性同性愛・女性同性愛の人物をたくさん登場させていました。
ゲイ雑誌「薔薇族」の対極・対応してできた「百合族」説
1971年(昭和46年)にゲイ雑誌「薔薇族」が創刊されました。
薔薇の赤い派手やかなイメージとともに、ゲイを赤い薔薇でたとえられていた風潮から、対極したレズは白色の百合の花を当てて「百合族」といわれはじめたという説があります。
「百合族」を命名したのは雑誌「薔薇族」の編集長・伊藤文學氏といわれています。
伊藤編集長が、薔薇・百合の隠語を作り上げて普及させたのはすごいですね!
百合の意味は女の子
女性の美貌や容姿を褒めることわざに「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」というものがあります。
女性の美しさをたとえる花の一つである百合も、女性同士のカップリングを「百合」と暗喩したきっかけ・後押しになったと考えられます。
百合は隠語として利用
近年、特にアニメや漫画のサブカルチャーの中で異性愛的な要素が少なく、女性同士の親密な関係や愛を描いたコンテンツを指す隠語として使われています。このようなコンテンツはしばしば「百合作品」と呼ばれます。
「百合」が隠語として利用される理由はいくつかあります:
- 表現の幅を広げる: アニメや漫画のファンが異性愛の恋愛に飽き足りない場合、同性愛的な要素を取り入れた作品は新しい表現の機会を提供します。このような作品は多様な性的指向や関係を探求できるため、ファンにとって魅力的です。
- タブーを扱う: 同性愛に対する社会的なタブーがある一方で、それを扱ったコンテンツが人気となることがあります。異性愛とは異なる視点から愛や友情を描くことで、新しい物語の可能性が開かれます。
- 女性キャラクターの強化: 百合作品はしばしば女性キャラクターの深化と強化に寄与します。彼女たちの感情、絆、成長を強調することで、物語の魅力が向上し、幅広い層の観客に訴えます。
- ファン層の拡大: 同性愛的な要素を取り入れたコンテンツは、異性愛者だけでなく、LGBTQ+コミュニティのメンバーにも受け入れられています。これにより、より多くの人々にファン層が拡大することがあります。
「百合」は、文化的に多様な視点を提供し、異なる性的指向のキャラクターとストーリーを探求する一つの手段として、アニメや漫画の世界で重要な存在となっています。
海外では百合とは言わない?
百合という隠語・言葉は日本発祥のため、海外で女性同士のカップリングを百合と言ったりはしません。
ちなみに薔薇のほうは海外でもゲイのたとえとして使われています。
百合とレズの違いは?
百合の場合には、女性同士の友愛で友情以上からプラトニック恋愛、性的な愛情まで幅広く定義がされています。
一方のレズは性的嗜好部分のみを指すような言葉なので、百合とレズを使い分けている人もいるのが現状です。
百合 (Yuri)
意味: 「百合」は、日本のアニメや漫画文化において使われる用語で、女性同士の親密な友情や愛情を描いた作品を指します。これらの作品では、しばしば女性キャラクター同士の深い友情や恋愛関係がテーマとして探求されます。ただし、性的な要素が含まれないことが一般的です。
性的要素: 通常、百合作品は性的な要素を含んでいないか、控えめに扱われます。百合の関係は、感情的なつながりや親密さに焦点を当てることが多いため、性行為が描かれることは少ないです。
レズビアン (Lesbian)
意味: 「レズビアン」は、性的指向を指す用語で、女性が女性に対して感情的な愛情や性的な興奮を感じる場合に使用されます。これは性的指向やアイデンティティに関する用語であり、個人の性的指向を表すものです。
性的要素: レズビアンの関係において、性的要素は重要な一部となります。レズビアンは同性愛者であり、性的な魅力や愛情が同性に向けられるため、性的な要素が含まれることが一般的です。
まとめ
要約すると、百合はアニメや漫画の作品において女性同士の親密な関係を描いたものであり、性的要素が含まれないか控えめであることが一般的です。一方、レズビアンは性的指向を表す用語であり、女性同士の性的な関係や愛情を指します。両者は異なる文脈で使用され、異なる意味を持ちます。